玄関の鍵交換にかかる費用やDIYで行うときのポイントと注意点
玄関の鍵交換の費用は、交換する鍵の種類によって異なります。 鍵にはシリンダー・プッシュプル・インテグラルとさまざまな種類があり、防犯面の高さにも違いがあります。 玄関の鍵はDIYで交換できますが、あくまで自己責任です。鍵のサイズが合わない、部品を紛失してしまったなどのトラブルに注意しましょう。 防犯性や仕上がりの面でも、玄関の鍵交換は専門業者に依頼することをおすすめします。
この記事では、玄関の鍵の種類と特徴、交換にかかる費用ほか、鍵交換をDIYで行うときの手段や注意点について詳しく解説いたします。 玄関の鍵を交換しようと思っている方は是非参考にしてください。

目次
- DIYによる鍵交換の目安費用
- 玄関の鍵の主な種類
- 防犯性の高い鍵の種類とは?
- 鍵交換の際には鍵の種類だけでなくドアの規格もチェックすべき
- 鍵交換の際、暗証番号式や生体認証式の鍵に交換する必要性はあるか?
- 玄関の鍵交換を検討すべきタイミング
- 玄関ドアの鍵交換を怠ることで想定されるリスク
- DIYで玄関ドアの鍵交換をする手順
- DIYで玄関ドアの鍵交換をするメリット
- DIYで玄関ドアの鍵交換をする際の注意点
- 玄関ドアの鍵交換を業者に依頼することのメリット
- 鍵交換を業者に依頼する料金相場や悪徳業者の見分け方
- 玄関ドアの鍵交換はどんな業者に依頼すべきか?そのポイント
- 玄関の鍵交換を業者に依頼するときの注意点
- 玄関の鍵交換におすすめのメーカー
- 玄関の鍵交換についてのよくある質問
- まとめ
DIYによる鍵交換の目安費用
玄関の鍵をDIYで交換する際にかかる費用は、選ぶ鍵の種類によって大きく異なります。
シンプルな構造のピンシリンダーやディスクシリンダーであれば、比較的リーズナブルな価格で入手でき、部品代は数千円台から始まることが一般的です。古い住宅などでよく見かけるインテグラル錠も、価格帯としてはそれに近い水準で、DIYでも手が出しやすいカテゴリといえるでしょう。
一方で、防犯性を重視したい場合に選ばれるディンプルシリンダーになると、構造が複雑なぶん価格も上がり、1万円を超えるものが多くなってきます。さらに、近年の新築住宅やマンションで増えているプッシュプル錠は、ハンドルごと交換する必要があるため、製品自体の価格が高額になりがちです。モデルによっては数万円〜10万円前後になることもあり、DIYで導入するには慎重な検討が必要です。
また、引き違い扉用の鍵もタイプによって幅があり、シンプルなものであれば1万円未満で済む場合もありますが、交換に手間がかかる複雑なタイプでは2万円程度まで費用がかかることもあります。
このように、DIYでの鍵交換は「どの鍵を選ぶか」によって費用が大きく変わります。予算を抑えたい場合は既存の鍵と同じ規格で交換できる製品を探すと安心ですが、防犯性とのバランスを考えることも忘れずに進めるとよいでしょう。
玄関の鍵の主な種類
玄関の鍵、とひと言でいっても、その種類は数多くあります。
玄関の鍵として特によく使われているタイプは、以下の4タイプです。
- シリンダー錠
- プッシュブル錠
- インテグラル錠
- 引き違い戸錠
- 装飾錠
- カードキー
- 暗証番号錠
- 生体認証錠
それぞれのタイプについて個別にご説明しましょう。
さまざまなタイプがあるシリンダー錠
シリンダー錠は、現在日本において玄関扉の鍵としてもっとも多く使用されているタイプの鍵です。鍵穴および、扉の内側にあるつまみ=サムターンで施錠すると、扉側面から閂(かんぬき)が出てきて、扉が開かなくなるという仕組みです。
鍵を差し込む鍵穴がある部分がシリンダーと呼ばれる部分で、このシリンダーには、実は非常に多くの種類が存在しています。
ここではシリンダー錠のなかでも特に主流となっているピンシリンダー・ディスクシリンダー・ディンプルシリンダーの3種類について、その特徴をご紹介します。
| ピンシリンダー | 鍵の片側にギザギザがついているのが大きな特徴。 シリンダーの内部、上と下それぞれにピンが入っており、鍵を差し込むとそのピンが所定の位置まで押され、鍵が回るという仕組みです。 シリンダー錠のなかでも安価なのがメリットですが、防犯性はそれほど高くありません。 |
|---|---|
| ディスクシリンダー | 鍵の両側にギザギザがついています。現在は廃盤になっている旧タイプであり、現在流通している鍵の両面にギザギザがついている鍵を使う錠前はロータリーディスクシリンダーという新しいタイプのものです。 ただのディスクシリンダーだった時代は構造が単純でピッキングなどにも非常に弱いという弱点がありましたが、現在流通しているロータリーディスクシリンダーは構造が複雑化している分、防犯性も向上し、ピッキングが比較的難しい鍵となっています。 価格も比較的お手頃なものが多く、防犯性とコストのバランスにすぐれている存在です。 |
| ディンプルシリンダー | 鍵にギザギザがついておらず、鍵の表面に、丸いくぼみがたくさんついているのが特徴です。 ロータリーディスクシリンダーよりもさらにはるかに構造が複雑で、鍵の複製自体も困難、シリンダー錠のなかでは最上級クラスの防犯性を誇るのが最大のメリットです。 鍵の複製は鍵業者のなかでも特殊な機器や技術を有しているところでしかできないので安全性は高いですが、その分スペアキーを作りにくいという不便さもあります。 また、ピンシリンダーやディスクシリンダー(ロータリーディスクシリンダー)なら1万円未満で買えるものも多いですが、このディンプルシリンダーは数万円クラスが主流となっており、シリンダー錠としてはかなり高額であるという点もデメリットとして挙げられます。 |

プッシュプル錠はハンドルを押し引きして開閉するタイプ
プッシュプル錠は、プッシュプルハンドルともいわれる存在で、ドアノブを回して開けるタイプの錠前とは異なり、ハンドルを押したり(プッシュ)、引いたり(プル)して、開閉するタイプのものです。
鍵の開け閉め自体は鍵穴に鍵を差し込んで回す必要がありますが、ドアノブを回す必要がなく、体でハンドルを押すだけでもドアが開くなど、利便性が高い点が大きな魅力です。
ただしこのプッシュプル錠は、ハンドルごと交換という形になる分、部品が大きいこともあって交換のための部品費用が高くつきがちです。
数万円ぐらいの価格が主流となっていますが、高価なプッシュプル錠ともなると10万円前後にもなることがあります。
インテグラル錠は古いアパートなどに使われていることが多い
インテグラル錠は、古いアパートの玄関扉などによく見られる、ドアノブとシリンダーが一体化したタイプのものです。鍵の形は片方にギザギザがついたタイプのものが主流となっています。
価格は数千円レベルと安価なのがメリットですがピッキングに弱く、現在の新築物件の玄関扉にこのインテグラル錠が採用されることはほとんどありません。
引き違い戸錠は引き違い扉に使われる
引き違い戸錠は、その名のとおり、引き違いタイプの玄関扉に使われる鍵です。
ただ、ひと言で引き違い戸錠といってもタイプはさまざまで、施錠する箇所も、扉の真ん中のみ、真ん中と両端、扉の片方だけ、扉の両端だけなど、ものによって違いがあります。
さらに、シリンダー部分のみ交換できるものもあれば、錠前をすべて取り替えなければいけないものもあります。 既存の引き違い戸錠が廃盤になってしまっていた場合、適合する錠前を探すのが非常に困難になる場合もありますし、完全に適合するものが見つからず、扉の穴に加工をほどこさなければ鍵交換すらできないというケースも少なくありません。
引き違い戸錠は、部品価格自体は2万円程度までで済むものが多いため、特段高価というわけではありませんが、交換可能な錠前を的確に見つけ出すことが難しいなど、ほかの鍵と比べると素人にとってはハードルが高いタイプの鍵となっています。
装飾錠は見た目のデザイン性を重視したタイプ
装飾錠は、機能面に加えて玄関ドアの外観デザインにもこだわりたい人に選ばれているタイプの鍵です。ハンドルと錠前が一体となっており、洋風・アンティーク調・モダンデザインなど、建物の雰囲気に合わせた装飾が施されているのが特徴です。
外見の美しさに重きが置かれる一方で、防犯性は内部に組み込まれているシリンダーの性能に依存します。見た目の重厚さに安心感を覚えるかもしれませんが、防犯性を高めたい場合は、ディンプルシリンダーなど強固な鍵と組み合わせて使うことが重要です。DIYでの取り付けも可能なものがある一方で、サイズや取り付け位置が特殊なものも多く、事前にしっかりと規格を確認しておく必要があります。
カードキーはタッチ式で開閉できる非接触型の鍵
カードキーは、交通系ICカードのような感覚で鍵の開閉ができる非接触型の鍵です。ドアのリーダー部分にカードをかざすことでロックが解除される仕組みになっており、鍵穴がない分、ピッキング被害に遭いにくいというメリットがあります。
紛失時にはカードの再発行や登録解除ができるため、物理的な鍵よりもセキュリティ管理がしやすい点も魅力です。ただし、電子制御によって動作するため、電池切れや停電の際には非常用の開錠方法が必要になります。カードの再登録や複製制限など、運用面での管理にも一定の知識が求められるため、導入前にはよく確認しておくと安心です。
暗証番号錠は鍵を持ち歩く必要がない便利な選択肢
暗証番号錠は、物理的な鍵を使わずに数字の入力だけでドアを解錠できる電子錠の一種です。鍵を持ち歩かなくて済むため、紛失のリスクがなく、小さな子どもや高齢者のいる家庭でも扱いやすいというメリットがあります。
防犯面でも、暗証番号の桁数を長くしたり、定期的に変更したりすることでセキュリティを高めることができます。ただし、番号を忘れてしまうと解錠できないという事態にもなりかねません。また、操作中の番号を他人に見られる「のぞき見リスク」や、電池切れ・故障時の対応方法についても考慮しておく必要があります。
生体認証錠は指紋や顔などの個人情報で開閉する高性能タイプ
生体認証錠は、指紋や顔・静脈などの生体情報を使って解錠する、最先端の電子錠です。登録された本人しか鍵を開けられない仕組みのため、セキュリティの高さは群を抜いています。
最近は指紋認証タイプが一般家庭にも普及し始めており、鍵や暗証番号を持ち歩かずに開閉できる利便性は大きな魅力です。ただし、ケガや乾燥などで指紋が読み取れないことがあるほか、電源トラブル時には使用できなくなるケースもあるため、予備の物理キーや緊急開錠手段を確保しておくと安心です。また、他の鍵タイプに比べて価格は高めで、導入時には本体費用と施工費の両方を考慮しておくことが重要です。
防犯性の高い鍵の種類とは?
「この鍵で本当に安心できるのだろうか?」と感じること、ありますよね。 玄関というのは、住まいの”顔”であると同時に”入り口”でもあります。だからこそ、鍵の種類によって防犯性に差が出るという仮説を立ててみました。そして実際、鍵の設計や構造を比べてみることで「防犯性が高い鍵とはどういうものか」が見えてきます。 ここではその検証結果を踏まえつつ、鍵の構成や機能面から「防犯性の高い鍵」を考えていきます。
まず前提として、空き巣の侵入手口として「鍵をピッキングする」「鍵穴を破壊する」「合鍵を使って侵入する」という方法が一定割合で報告されています。例えば、ある解説では「鍵穴の構造が単純なタイプだと、ピッキング・鍵穴破壊で5分以内に開けられる可能性がある」と指摘されています。このため「鍵選び=侵入に時間をかけさせる」という観点が、防犯性を高める上で重要になるという仮説に至ります。 では、実際にどのような仕様や機能が「防犯性を高める鍵」なのか。まずひとつめに、鍵の中身、つまり「シリンダーの構造」が鍵を握っています。真っ先に挙げられるのが、いわゆるディンプルキーや高精度シリンダーといったモデルで、これらはピッキング耐性・鍵穴破壊耐性に優れているというデータがあります。
次に、外部から”合鍵を簡単に作れない仕組み(登録制など)”や”鍵穴そのものを物理的に見せない/鍵穴がない構造(電子錠・スマートキー等)”という機能も、防犯性を語るうえで無視できない要素です。 最後に、鍵や錠前を交換するだけでなく、ドア本体・取付け状態・使用状況など「鍵+建材+運用」の面まで含めて検討しておくことが、防犯性向上に当たっては現実的な対策といえます。
このように、「防犯性が高い鍵」とは単に”高価な鍵”というだけではなく、構造・機能・運用という三つの視点を通じて選ぶ必要があるという結論に至ります。以後、実際の鍵の種類を見極めるためのヒントや考え方を、もう少し深掘りしていきましょう。
ピッキング耐性が高いかどうか
防犯性を考えるうえで、まず注目したいのがピッキングに対する耐性です。ピッキングとは、特殊な工具を使って鍵穴の内部構造を操作し、正規の鍵なしで解錠する不正手段のこと。構造がシンプルな鍵ほど、わずか数十秒で開けられてしまう可能性があり、古いタイプのピンシリンダーやディスクシリンダーは特に注意が必要です。
一方で、ディンプルシリンダーやロータリーディスクシリンダーといった、内部に複数のピンやディスクを組み込んだ構造の鍵は、ピッキングが極めて困難とされています。防犯建物部品(CP認定)を取得している鍵であれば、ピッキング試験をクリアしたものも多く、ひとつの目安になります。鍵を選ぶ際は、「どの程度の時間、ピッキングに耐えられる設計か?」という視点で比較すると、セキュリティへの安心感も高まるでしょう。
鍵穴破壊への耐久性があるか
鍵穴そのものを物理的に破壊して侵入する手口にも備える必要があります。たとえば、ドリルなどで鍵穴を直接破壊する「ドリリング」や、工具で回しながら壊す「バンピング」などの手法は、短時間で解錠されてしまう恐れがあります。
こうした攻撃に強い鍵には、シリンダー内部に「破壊防止プレート」や「超硬ピン」などの補強が組み込まれているものが多く、物理的な攻撃に対する耐久性が大きく異なります。また、最近の電子錠にはそもそも鍵穴が存在しないモデルもあり、破壊手段そのものを成立させないという点で防犯性に優れています。 「破壊されにくい鍵」であるかどうかは、カタログスペックだけでは見えにくい部分もあるため、購入時には各メーカーが提供している防犯試験情報やCPマークの有無を確認すると安心です。
さまざまなタイプがあるシリンダー錠
第三者による合鍵の不正コピーも、見落としがちなリスクのひとつです。とくに賃貸物件や中古住宅では、以前の居住者や業者が合鍵を保有していた可能性があるため、「今の鍵は誰がコピーを持っているか分からない」という不安がつきまといます。 その点で、防犯性の高い鍵は、合鍵の複製方法にも配慮されています。たとえば、正規の登録カードがないとスペアキーの作成ができない”所有者限定型”のディンプルキーや、メーカーに直接依頼しなければ作成できない”管理登録制キー”は、無断複製を防ぐうえで非常に有効です。
さらに、そもそも物理的な鍵が存在しないカードキー・暗証番号錠・生体認証錠なども、「合鍵を持たれる」というリスクそのものを排除できる手段です。「合鍵をつくられにくいかどうか」は、実際のセキュリティ管理を続けるうえでとても現実的なチェックポイントといえるでしょう。
鍵交換の際には鍵の種類だけでなくドアの規格もチェックすべき
鍵交換の際は、既存の鍵と同じ種類の鍵、既存の鍵に近いタイプの鍵を買って取り替えるというのが基本スタイルであるため、既存の鍵はどのタイプなのか、その種類を事前にきちんと調べておくことは非常に重要です。
そして鍵交換は、鍵の種類さえ調べておけば大丈夫というわけではありません。
もちろん、同じメーカーで型番もまったく同じ鍵に取り替えるというだけなら問題はありません。しかし実際の鍵交換においては、既存の鍵がつけられてから年月が経っているため、同じメーカーであっても型番は異なるというケースがほとんどですし、場合によってはメーカーすらも変えることもあります。
そのような場合は「鍵(錠前)をドアに取りつけられなければ話にならない」という大前提を踏まえた準備が必要です。今ある鍵に似たタイプの鍵を探すというだけでなく、今使っているドアに適した鍵を探すことも必要になってくるため、ドアの規格についても、事前に調べておく必要があるわけです。
ドアの規格としてチェックしておくべき項目は、以下の4点です。
- ドア側面の厚み
- バックセット(ドアの端から錠前の中心までの距離)の長さ
- フロント(扉側面についている、かんぬき部分などが出てくるプレート)の長さ
- フロントのプレートを止めているビスの間隔
型番やメーカーが違う鍵に交換する場合は、これら4つのサイズを事前に正確に計測しておき、この計測値に適合する鍵=今あるドアの規格に合う鍵を探して選ぶことが必要です。
鍵交換の際、暗証番号式や生体認証式の鍵に交換する必要性はあるか?
せっかく玄関扉の鍵交換をするのであれば、よりセキュリティ性の高い鍵に交換したい、と考える人も少なくありません。
セキュリティ性の高い鍵といえば、暗証番号式の鍵や指紋認証などの生体認証式の鍵などが思い浮かびますが、鍵交換の際にこうした高セキュリティの鍵に交換する必要性はあるのでしょうか。
暗証番号式の鍵や生体認証式の鍵に交換することのメリットやデメリットを知ったうえで、こうした鍵への交換の必要性についても考えてみましょう。
暗証番号式の鍵のメリットとデメリット
暗証番号式の鍵のメリットとしてはまず、鍵を持ち歩く必要がないということが挙げられます。鍵を紛失してしまいやすい人にとっては、暗証番号式は非常に便利です。
また、暗証番号入力ミスを繰り返すと自動ロックがかかるように設定されていれば、暗証番号が偶然などで破られる確率はかなり低く、セキュリティの面でも大きなメリットがあります。
ただし、当然のことながら暗証番号を忘れてしまった場合は解錠できないというデメリットもあります。暗証番号など忘れるわけがない、と思っている人が多いですが、セキュリティ向上のために長い暗証番号を設定している場合や、定期的に暗証番号変更などをしている場合は、その番号をうっかりと忘れてしまうケースも少なくありません。
だからといって暗証番号を忘れないようにメモ書きなどしていると、それを他人に見られた場合あっさり解錠されてしまいます。 解錠時のキー操作を他人に見られてしまった場合も解錠されてしまうことになるなど、暗証番号式は暗証番号管理そのものにおける難しさがあります。
暗証番号式の落とし穴としてはもうひとつ、停電時や電池切れになったときは使えないというのも挙げられますので、これも注意が必要です。
生体認証式の鍵のメリットとデメリット
指紋認証など、生体認証式の鍵についても、鍵を持ち歩く必要がないというのは大きなメリットです。
また、かなりの精度で個人を特定できるため、登録している人以外が解錠するのはきわめて困難ということで、セキュリティ性が特に高いというのも生体認証式の強みです。
ただし、生体認証式の鍵は基本的に高額となっており、部品代だけでも10万円以上のものが圧倒的に多く、ものによっては数十万円もするというコスト面のデメリットがあります。
また、たとえば指紋認証の場合、指先をケガしてしまったり、ヒビ割れなどがあった場合はうまく読み取ってもらえないことがあります。さらに、これはあまり知られていないことですが、実は指紋はやろうと思えば複製も不可能ではありません。
使用者が触った部分に細かい粉末をつけてそこにセロハンテープなどを貼ってはがす、という方法でも、指紋は簡単に採取できてしまいます。
そして採取した指紋をデータ化し、それを3Dプリンターで出力するなどすれば、指紋の複製もできてしまうのです。
指紋はたとえ双子でも同じ指紋ではない、という事実があるからこそ絶対安心と考える人は少なくありません。実際には複製も不可能ではないという点で、完全無欠のセキュリティにはならないということを理解しておくことが大切です。
あと、指紋認証以外の生体認証といえば静脈認証や虹彩認証などもありますが、これらを採用している玄関鍵自体を見つけること自体が困難というデメリットもあります。
そして生体認証式の鍵も暗証番号式の鍵と同様に、停電時などは使えないという弱点があることも忘れてはいけません。
暗証番号式や生体認証式にこだわる必要性はそれほどない
玄関の鍵交換をする際に、よりセキュリティ性の高い鍵に変えたいと考えるのは自然なことですが、だからといって暗証番号式や生体認証式などにこだわる必要性はあまりありません。
これらの鍵は確かに高セキュリティというメリットはありますが、従来の鍵とはタイプが違いすぎる分、交換作業自体が困難になりやすいことや、停電時などの不自由さ、費用の高額さなど思わぬデメリットを抱えている、といった面もあります。
総合的に考えると、これまで使い慣れたタイプの鍵に交換したほうがストレスなく使える可能性が高いので、基本としてはそちらを選ぶほうがおすすめです。
暗証番号式や生体認証式にこだわらなくとも、たとえばシリンダー錠を交換する際にはシリンダー錠のなかでも防犯性の高いディンプルシリンダーを選ぶ、などという方法を使えばそれだけで以前よりセキュリティ性を高めることができます。
玄関の鍵交換を検討すべきタイミング
玄関の鍵は、「1度取り付ければ半永久的に使用できる」というわけではありません。鍵を交換せず放置してしまうと、鍵の防犯性・安全性が低下します。どのような鍵であれ、「鍵の替え時」を逃さないことが大切です。
ここからは、玄関の鍵交換を検討すべき4つのタイミングについて紹介します。
玄関の鍵を紛失してしまったとき
玄関の鍵を紛失してしまったときは、速やかに新しい鍵に交換しましょう。
マスターキーを落としても、「スペアキーを使えば問題ない」などと考える人もいるかもしれません。しかし鍵を紛失したまま放置すると、防犯面のリスクが高くなります。
自分では「落とした」「なくした」と思っていても、盗まれてしまった可能性は否定できません。空き巣に入られたり強盗と鉢合わせしたりするリスクを考えれば、早急に鍵交換を行った方が安心です。
また、不審者やストーカーがあなたの鍵を盗み、スペアキーを作った可能性もあります。「鍵を紛失したけれど、数日後に見つかった」という場合でも、鍵の防犯性能は落ちていると考えましょう。
「どうしてなくなったのか分からない」「探したはずのところから鍵が見つかった」などの場合は、たとえ鍵が見つかったとしても、鍵を交換しておくことをおすすめします。
鍵に劣化のサインが表れたとき
一概にはいえませんが、鍵の平均寿命は約10年といわれています。鍵を使い始めてから長い時間がたっている場合は、そろそろ交換のタイミングです。
例えば鍵にさび・ヒビ・変形などが起こっている場合は、劣化のサインが表れています。「鍵を挿しても回りにくい」「固い」などがある場合も、劣化している可能性が高いでしょう。
鍵の調子が悪いことを知りながら使い続けると、ある日突然鍵が回らなくなるかもしれません。だましだまし使うにも、限界があると理解してください。
ただし鍵は、汚れやホコリによって回りにくくなることもあります。
鍵周辺の掃除を怠っていた場合は、まず鍵穴を掃除してみましょう。エアダスターや掃除機を使って汚れやホコリを吸い取り、最後に潤滑油を挿してみてください。
これでも鍵の調子が良くならない場合は、劣化による不具合の可能性大です。なるべく早めに鍵を交換することをおすすめします。
中古物件・賃貸物件に引っ越すとき
中古物件の購入では、鍵の交換は買主負担が基本です。物件引き渡しを受けたら、鍵の交換を行いましょう。
前の持ち主から鍵を受け取ったとしても、それが全てとは限りません。もしかすると相手はまだスペアキーを持っている可能性があります。不安を感じながら暮らすよりは、物件購入のタイミングで鍵を交換した方が安心です。
一方賃貸物件に入居する場合、鍵の交換は管理会社や大家が行うこととされています。しかしこれは、義務というわけではありません。物件所有者が「鍵の交換をしない」という主義の場合は、古い鍵がそのまま使われている可能性があります。
賃貸物件に入居する際は、鍵の交換が済んでいるかどうか確認しましょう。交換されていない場合は、入居前に交換しておくのがおすすめです。
なお賃貸物件入居時の鍵の交換費用は、貸主が払うケースと借主が払うケースのどちらもあり得ます。まずは管理会社や大家に詳細を聞き、どちらが鍵の交換費用を持つか決めてください。
ただし入居後に鍵を交換したくなった場合は、基本的に借主負担となります。勝手に交換するとトラブルになるため、この場合もまずは管理会社や大家に相談することが必要です。
防犯面に不安があるとき
家の鍵として、片側にギザギザが付いている「ピンシリンダー」や、両側にギザギザが付いている「ディスクシリンダー」を使ってはいませんか?
これらの鍵は構造がシンプルな分ピッキング被害に遭いやすく、プロならわずか数秒で開けてしまいます。玄関に古いタイプの鍵が使われている場合は、防犯対策が十分とはいえません。
玄関の鍵がピンシリンダーやディスクシリンダーの場合は、ディンプルシリンダーに交換するのがおすすめです。ディンプルシリンダーは、くぼみとピンの組み合わせを採用した複雑な構造が採用されています。
ピッキングのプロでも開けるのは難しく、素早く開けるには鍵を壊すしかありません。
ピッキングによる空き巣犯の多くは、「5分以内に開かない鍵はあきらめる」といわれています。複雑で開けにくいディンプルシリンダーなら、空き巣被害のリスクをグッと抑えられるはずです。
玄関ドアの鍵交換を怠ることで想定されるリスク
鍵交換を先延ばしにしてしまうと、「今は大丈夫だろう」という安心感が、実は見えないリスクを呼び込んでいる可能性があります。実際に鍵の劣化や仕様の古さ、紛失後の対応のずれなどが原因で、防犯性能が想定よりも大きく落ちてしまうケースが報告されています。 ここではその仮説を検証しながら、交換を怠ることで起こりうる主なリスクをご紹介します。
まず、鍵そのものの構造が古いまま使われていると、最近の侵入手口に対する耐性が十分ではないという問題があります。たとえば、旧型のピンシリンダーやディスクシリンダーは、構造が単純なため、ピッキングや鍵穴破壊による侵入に比較的早く対応されてしまう可能性があります。
次に、鍵の紛失・合鍵の流出といった”鍵管理”に関するリスクも無視できません。鍵をなくしたまま交換しないでいると、第三者がコピーした合鍵で侵入されてしまう可能性や、前住者がその鍵を持ち続けている環境がそのままになっているという状況も考えられます。こうした状態を放置することは、物理的な防御ラインが事実上崩れていることを意味します。さらに、鍵自体が長年使用されることで摩耗・さび・変形が進むと、使い勝手が悪くなるだけでなく、いざというとき鍵が回らない・ドアが閉まらないというトラブルに発展することもあるのです。
また、鍵交換を怠ることで被る損害は、単に「鍵を新しく買う費用」だけに留まりません。万が一侵入されてしまった際には、家財の損害、精神的ダメージ、保険が適用されない場合の支払いなど、トータルで見たコストが想定を超えるケースがあります。実際、「鍵交換を放置した結果、侵入リスクが上がる」と指摘する声も上がっています。ですから、「鍵がまだ使えているから大丈夫」という思い込みをしていると、長期的に見て割高になる可能性があると考えられます。
鍵交換を先送りすることで得られる”安心”を過信してしまうと、自宅を守るために必要な”作業のタイミング”を逃してしまうことがあります。鍵の交換や仕様の見直しは後回しにしやすい作業ですが、暮らしの安全を守る上では、むしろ”少しの不安”を感じた段階で動き出すことが、最終的な安心につながると言えるでしょう。
DIYで玄関ドアの鍵交換をする手順
DIYで玄関ドアの鍵交換をする際のおおまかな手順は以下のとおりとなります。
- 工具および交換用の新しい鍵(錠前)を用意する
- 既存の鍵を取り外す
- 新しい鍵を取りつける
それぞれの手順についてご説明しましょう。
1. まずは工具と新しい鍵を用意しよう
鍵交換をするためにはまず、必要な工具と交換用の新しい鍵(錠前)を用意しなければいけません。
まず、工具については、どのようなタイプの鍵であれ、基本的にはドライバー(プラスとマイナス)が必要です。マイナスドライバーは先が細いタイプのものが使いやすいです。
また、シリンダーがピンで固定されている鍵の場合は、そのピンを抜くためにペンチまたはプライヤーも必要になりますので、これも最初から準備しておくといいでしょう。
工具の用意ができたら、次は新しい鍵の用意です。既存の鍵はどんなタイプでどんなサイズか、それをきちんと確認したうえで、新しい鍵を購入しましょう。
新しい鍵を買う際に失敗リスクを低減するポイントのひとつとして挙げられるのは、交換用の鍵も、既存の鍵と同じメーカーのものをなるべく選ぶということです。
同じメーカーの鍵で寸法が合っているものであれば、鍵自体の仕組みなども非常に似たものとなっているため、交換作業がスムーズに行きやすいというメリットがあります。
2. 既存の鍵を取り外そう
既存の鍵は基本的にドライバーを使ってビスをすべて取り外してから錠前を取り外します。ピンなどでシリンダーが固定されている場合はペンチで抜きましょう。
この既存の鍵の取り外しは、多くの場合、ビスをとにかく取り外していくことを心がければ意外と簡単にできます。 この取り外し作業については、たとえ驚くほどスムーズにいったとしても、機械的にサクサク進めるのではなく、その手順をしっかりと自分の目と手で覚えるようにしながらじっくりと取り外すようにすることが大切です。
なぜなら、取り外しの際の手順をきちんと理解しているかどうかで、新しい鍵の取りつけ作業のスムーズさも違ってくるからです。
「新しい鍵の取りつけ作業は、取り外し作業の逆再生のようなもの」と考えてもらうと、取り外し作業の際に作業手順をしっかりと確認しながらやることの大切さが理解できるかと思います。
サクサクと作業するということにこだわるのではなく、肝心の取りつけ作業で失敗をしないために取り外しの工程は意識的に丁寧かつゆっくりとやる、ということを心がけましょう。
3. 新しい鍵を取りつけよう
既存の鍵の取り外しが終わったら、いよいよ新しい鍵の取りつけです。
新しい鍵の部品を箱から出したら、白い布の上など、細かい部品でもよく目立って見えるような状態になるように置きましょう。こうすることで、部品紛失のリスクが低くまります。
そして、先ほどの取り外し作業の逆再生をするようなイメージで、説明書を見ながら新しい鍵を取りつけていきます。
説明書の説明だけで分かりにくいときは、取り外し作業の逆の手順でつけていく、ということを念頭に、先におこなった取り外し作業の状況を今一度頭に思い浮かべるようにするといいでしょう。
DIYで玄関ドアの鍵交換をするメリット
これまで見たとおり、鍵の交換工程は非常にシンプルです。DIYに慣れた人なら、さほど時間をかけずに交換できるでしょう。
ここからは、DIYで玄関ドアの鍵交換をするメリットを紹介します。
鍵交換のコストを抑えられる
鍵の専門業者に交換を依頼した場合、部品代にプラスして工賃が必要です。このほか、会社によっては自宅までの交通費を請求されることもあるでしょう。DIYで鍵の交換を行えば、業者に支払う工賃や交通費がゼロになります。
工賃は、会社の設定や鍵の交換の難易度によってさまざまです。一概にはいえませんが、約1万円からとする業者が多いようです。
すなわち鍵の交換をDIYで行えば、コストを1万円以上節約できる計算になります。
業者の都合に合わせる必要がない
鍵の交換をDIYで行えば、自分の好きなタイミングで作業できます。「鍵を交換したい」と思ったときに取り組めるため、予定を変更したり業者の都合に合わせたりする必要がありません。忙しい人・自由な時間を取りにくい人には、大きなメリットといえるでしょう。
そもそも業者に鍵の交換を依頼する場合は、「見積もり」「交換」という流れになります。実際に交換してもらうまでに時間がかかることが多く、業者を決めるだけでも大変です。
自分のペースで納得のいく鍵交換を行いたい場合は、DIYが有力な選択肢の一つです。
他人の手を借りずに済む
玄関の鍵は、家庭セキュリティの要といえます。防犯意識の高い人は、業者にさえ「鍵に触って欲しくない」と考えることもあるでしょう。
DIYで鍵の交換を行えば、全ての工程に他人が入ることはありません。家の中を見られたり詮索されたりする恐れがなく、気分的に安心できます。
DIYで玄関ドアの鍵交換をする際の注意点
DIYで玄関ドアの鍵交換をすることは可能ですが、事前に理解しておくべき注意点もいくつかあります。
まず絶対に理解しておかなければいけないのは、DIYによる鍵交換の失敗はすべて自己責任であるということです。
- 鍵(錠前)のサイズを間違えてしまって取りつけられない
- 無理やり取りつけたもののドアが閉まらない
- 取りつけ作業時に小さなビスを紛失してしまった
- 返って修理費用がかさんでしまうリスクもある
などはよくありがちなミスですが、こうしたミスによる鍵の買い替え費用やビスの調達などはすべて自己責任でやらなければいけません。
ここから、それぞれの注意点について詳しくお伝えします。
鍵(錠前)のサイズを間違えてしまって取りつけられない
鍵交換をDIYで行うとき、もっともよくある失敗のひとつが「サイズ違い」です。見た目が似ているからといって安易に購入してしまうと、実際のドアの厚みやビスの位置、バックセットの長さなどが合わず、取りつけ自体ができないという事態に直面します。パッケージや商品説明だけで判断せず、既存の鍵を慎重に採寸し、メーカーや型番が一致しているかを必ず確認してから購入することが大切です。サイズが少しでも合わないと、取りつけどころか返品もできない可能性があるため、最初の段階でのミスが大きな損失につながることを意識しておく必要があります。
無理やり取りつけたもののドアが閉まらない
鍵本体をどうにか取りつけたとしても、それで安心してしまうのは早計です。サイズが微妙に合っていない状態で無理に設置すると、ドア自体が正常に閉まらなくなることがあります。たとえば、閂(かんぬき)の位置がずれてしまったり、ドアフレームとの干渉で締まりが悪くなったりするケースです。防犯性はもちろんのこと、日常的な使い勝手にも大きな支障が出るため、「取りつけられたからOK」ではなく、取りつけ後の動作確認まで含めて安全かつ正確な作業が求められます。違和感がある状態で使い続けると、鍵やドアそのものを痛めてしまうこともあるため注意が必要です。
取りつけ作業時に小さなビスを紛失してしまった
鍵交換に慣れていない方にとって、意外と多いのが「部品の紛失」です。とくに小さなネジやバネ、固定ピンなどは、手元から転がって見失いやすく、失くしてしまうと鍵の機能自体が成立しなくなることもあります。また、メーカーによっては専用形状のネジを使っていることもあり、代替品が入手しづらいケースもあります。作業前に白いタオルなどの上に部品を並べ、作業スペースを整理しておくことで防げるトラブルですが、万が一のときは追加の部品購入や、最悪の場合は鍵自体を再購入する必要が出てくる可能性もあります。
返って修理費用がかさんでしまうリスクもある
「費用を抑えるつもりでDIYに挑戦したのに、結果的に高くついてしまった」という話は珍しくありません。たとえば取りつけミスによってドアや枠を傷つけてしまったり、誤って購入した鍵を返品できずに買い直したりといった二重の出費が発生すると、業者に最初から依頼した場合よりも高額になることがあります。鍵はセキュリティに直結する重要な部品であるため、販売店側でも一度購入された鍵の返品を原則不可とすることが多く、購入時点での判断ミスがリスクに直結します。安く済ませたいという気持ちは理解できますが、DIYは”費用を削減する手段”であると同時に、”すべての責任を自分で負う行為”であることも忘れてはいけません。
玄関ドアの鍵交換を業者に依頼することのメリット
ここまでDIYによる玄関の鍵交換の手順や注意点などについてご説明してきました。手順や注意点を見てDIYでの玄関ドアの鍵交換に少しでも不安があると感じた場合は、無理にDIYでやることにこだわるのではなく、鍵交換を得意とする専門業者に依頼することをおすすめします。
専門業者に鍵交換を依頼すると、DIYでやるよりも費用が高くついてしまうという理由で、業者に依頼することをためらう人も少なくありません。しかし、良心的な業者をきちんと選ぶことさえできれば、作業料金や出張料金などで法外な費用を請求されることはありません。
業者に鍵交換を依頼する最大のメリットは、やはりなんといっても作業内容や仕上がりに対する信頼感が違うということです。
ドアと鍵の状態を見たうえで交換に適した鍵を適切に判断してくれるだけでなく、素人のDIY作業と比べて失敗のリスクもほとんどありません。
素人のDIYによる鍵交換の場合、 「自分でやろうとチャレンジしてみたものの失敗し、また鍵交換のための部品を買い直ししなければいけなくなった」 「作業時にドアを破損してしまい、ドアの補修をしなければいけなくなった」 などという事態が発生する可能性があります。安く済ませるはずのDIYが、業者に依頼するよりも高くついてしまう結果になるということさえあるのです。
DIYによる玄関の鍵交換は、意外と手間がかかるうえに、失敗などのリスクもはらんでいるということです。
これまでここで鍵交換の手順などをご説明してはきましたが、それでも本来はDIYという方法は、決しておすすめできる方法ではありません。
玄関の鍵というのは防犯のためにも重要な存在ですし、さらに玄関扉というのは見た目の良さも重要なだけに、施工状態に不安の残る仕上がり、見た目の悪い仕上がりにしないことが大切です。
そうした要素を踏まえると、やはり可能なかぎりDIYでの鍵交換よりも業者に依頼しての鍵交換のほうを前向きに検討することを強くおすすめします。
鍵交換を業者に依頼する料金相場や悪徳業者の見分け方
思わぬシーンで必要になるのが鍵に関する専門業者ですが、安心して依頼できるところもあれば、中には悪徳業者も存在しています。実際の相場に比べて高額請求されることもあり注意が必要なのですが、実態や具体的な手口を知ることで防ぎやすくなるでしょう。 いざという時に安心して依頼できるように見分け方などを把握しておきましょう。
鍵開けにかかる料金相場
住宅の鍵 作業料金
| 玄関の鍵開け | 縦ギザギザキー(普通の鍵) | 8,000円~15,000円 |
| 防犯シリンダー・特殊開錠 | 15,000円~25,000円 | |
| 破壊開錠 | 15,000円~25,000円 | |
| 室内の鍵開け (トイレ・お風呂場など) | 鍵穴がある場合 | 8,000円~12,000円 |
| 鍵穴がない場合 | 8,000円~12,000円 | |
| 破壊開錠 | 9,000円~15,000円 | |
| 鍵の修理 | 修理(動きが悪いなど) | 8,000円~10,000円 |
| キー折れ(中で鍵が折れている) | 8,000円~12,000円 | |
| 鍵穴の異物除去(はりがね/木の枝) | 8,000円~12,000円 | |
| 鍵の交換 ~シリンダーのお取替え~ | ギザギザキー(普通の鍵) | 13,000円~18,000円 |
| 防犯向上シリンダー(泥棒対策) | 16,000円~25,000円 | |
| 特殊錠(装飾錠前など) | 26,000円~45,000円 | |
| 補助錠取り付け | 5,000円~38,000円 | |
| 面付本締錠 | 21,000円~38,000円 | |
| 鍵の作成 (カギが1本も無い場合の鍵の製作) | ギザギザキー(普通の鍵) | 13,000円~18,000円 |
自動車の鍵 作業料金
| 自動車の鍵開け | ギザギザキー(普通の鍵) | 8,000円~12,000円 |
| ハイセキュリティー | 11,000円~18,000円 | |
| 特殊キー(内溝/外溝/ウェーブ) | 11,000円~25,000円 | |
| 鍵穴で鍵が折れてしまった | キー折れキー抜き | 8,000円~25,000円 |
| 鍵の作成 (カギが1本も無い場合の鍵の製作) | ギザギザキー(普通の鍵) | 13,000円~18,000円 |
| 内溝キーもしくはハイセキュリティー車 | 25,000円~35,000円 | |
| ギザギザキー+イモビ有り (車種と年式により異なります) | 38,000円~55,000円 | |
| 特殊キー+イモビ有り (車種と年式により異なります) | 45,000円~55,000円 | |
| スマートキー作成 (車種と年式により異なります) | 45,000円~55,000円 |
バイクの鍵 作業料金
| バイクの鍵開け | バイクメットイン | 8,000円~9,000円 |
| バイクシャッターキー | 4,000円~10,000円 | |
| 鍵が折れてしまった | キー折れキー抜き | 4,000円~18,000円 |
| 鍵の作成 (カギが1本も無い場合の鍵の製作) | ギザギザキー(普通の鍵) | 13,000円~15,000円 |
| バイクシャッターキー | 8,000円~10,000円 |
金庫の鍵 作業料金
| 金庫の鍵がない(鍵開け) | 家庭用金庫 | 4,000円~9,000円 |
| 業務用金庫 | 8,000円~15,000円 | |
| 破壊開錠 | 11,000円~18,000円 | |
| 金庫のダイヤル (暗証番号)が分からない | 家庭用金庫3枚座の場合 | 4,000円~8,000円 |
| 家庭用金庫4枚座の場合 | 13,000円~18,000円 | |
| 業務用金庫 | 30,000円~50,000円 | |
| 破壊開錠 | 11,000円~18,000円 | |
| 金庫の鍵交換(シリンダー錠) | ギザギザキー(普通の鍵) | 13,000円~18,000円 |
| 防犯向上シリンダー(泥棒対策) | 18,000円~23,000円 | |
| 金庫ダイヤル | 暗証番号の変更 | 8,000円~15,000円 |
| 金庫ダイヤルの交換 | 15,000円~50,000円 |
店舗・事務所の鍵 作業料金
| 玄関の鍵開け | ギザギザキー(普通の鍵) | 8,000円~12,000円 |
| 防犯シリンダー・特殊開錠 | 13,000円~20,000円 | |
| 破壊開錠 | 15,000円~18,000円 | |
| 事務機器 | ロッカー/机/たんすの鍵開け | 8,000円~12,000円 |
| 1本もない鍵の製作 | 13,000円~18,000円 | |
| 室内の鍵開け (トイレ・お風呂場など) | 鍵穴がある場合 | 8,000円~10,000円 |
| 鍵穴がない場合 | 8,000円~10,000円 | |
| 破壊開錠 | 11,000円~13,000円 | |
| 鍵の修理と取り付け | 修理(動きが悪いなど) | 8,000円~10,000円 |
| キー折れ(中で鍵が折れている) | 8,000円~12,000円 | |
| 鍵穴の異物除去(はりがね/木の枝) | 8,000円~12,000円 | |
| ギザギザキー(普通の鍵) | 11,000円~15,000円 | |
| 防犯向上シリンダー(泥棒対策) | 18,000円~23,000円 | |
| 特殊錠(装飾錠前など) | 30,000円~35,000円 | |
| 補助錠取り付け | 5,000円~15,000円 | |
| 面付本締錠 | 21,000円~28,000円 |
悪徳鍵業者の手口
悪徳業者は金額や作業についての質問をされても明確に返答することが少なく、うまくはぐらかすことが多いです。これは必要以上の金額をぼったくるためであったり、そもそも技術力が不足しているから返答できないということもあります。基本的な手口は、電話の段階や料金表に記しているものは比較的安いものの、実際に請求されるときには高額になっていることが多いです。安心できる業者の場合は、わかりやすい料金表を設けて、見積もり価格よりも高くなりそうな場合にはあらかじめその旨を伝達してくれるところが多いです。 特に鍵のメーカーや型番、現在起こっているトラブルの具体的な状況を聞かないで修理可能だとすぐさま判断するようでは信頼性に欠けます。依頼電話の段階では依頼のハードルを低く見せ掛け、到着して以降は逆に修理のハードルを非常に高く見せようとするところは要注意です。 悪徳業者によってそれぞれ手口は異なるものの、これらのやり方でぼったくり行為を行おうとするところは一定数ありますから気をつけましょう。
悪徳鍵業者のトラブルの具体例
日本全国にある悪徳業者による高額請求事例には次のようなものがあります。
電話見積もりと全く違う金額を告げられた
鍵トラブルで業者に連絡をし電話見積もりで告げられた金額と作業後に請求された金額が大きく違うというケースです。状況に応じて追加の作業が必要な場合は、金額をあらかじめ依頼者に確認した上で作業に取りかかるのが常識ですし、そもそも追加作業などしておらず当初の見積もり通りの作業遂行だけでぼったくりを行う業者もいるので注意が必要です。
見積もり前に勝手に作業をはじめ高額請求された
状況によっては実際に現場を見てみないと詳細見積もりができないケースがありますが、一般的には作業前の段階できちんと金額を伝え承諾を得ることになります。しかし見積もりなどをせずに勝手に作業を開始し、終了後にありえないような高額請求がなされることも少なくないようです。
シリンダーを破壊してそのまま音信不通
技術力が未熟な業者に任せてしまうと鍵だけではなくて、ドア部分にはめ込まれているシリンダーを破壊しかねません。交換の必要があるので大きな出費になりますが、責任を認めようとせず音信不通になる業者も実際に存在しています。
直せないふりをして新品交換させようとする
比較的難易度が低い開錠作業でもわざと難しいふりをし作業料をつり上げる、シリンダー自体を交換するしかないと伝えて本来は不要な新品交換をさせるケースも見られます。例えば数千円程度で済む修理でも、新品に交換してしまうと数万円から場合によっては10万円以上必要になることもあるので要注意です。 以上が鍵に関するトラブルの具体例ですが、良心的な価格できちんと仕事を行う専門業者はたくさんいます。見極めさえできれば、いざというときに安心して利用することができるでしょう。
玄関ドアの鍵交換はどんな業者に依頼すべきか?そのポイント
玄関ドアの鍵交換をするなら、DIYでやるよりも業者に依頼したほうが安全確実でおすすめです。
ただし、鍵交換業者のなかには悪徳な業者が存在することも残念ながら事実です。どの業者に依頼するか、その選び方のポイントを押さえておくことは非常に大切です。
玄関ドアの鍵交換を業者に依頼する場合は、以下のポイントをすべてクリアできているかどうかをチェックしましょう。
- 見積もりが無料であること
- 見積もり後は、追加請求などをしないことを明言してくれていること
- 施工時のドア破損など、万が一の事態が発生した場合も損害賠償に応じてくれること
悪質な業者の場合、作業料金などは安く見せかけておいて高額な見積もり料金を別途請求する、見積もり後に何だかんだと理由をつけてどんどん追加料金を上乗せしてくる、施工ミスなどが発生しても責任を取ろうとしない、などといったトラブルを起こす可能性が非常に高いでしょう。
この3点のポイントだけでもしっかりチェックしておけば、悪徳業者に引っかかってそうしたトラブルに巻きこまれるリスクをかなり低減することができます。
そして業者がこの3点のポイントを守れるかどうかについては、業者に問い合わせて口約束で確認するのではなく、実際にホームページなどにこうしたことを守れる趣旨が明記されているかどうかをしっかりとチェックするよう心がけましょう。
ホームページ上にこれら3点についての記載が一切なく、聞かれたときだけ口頭で答えるというスタイルをとっている業者は、あとからいったいわないのトラブルを発生させるリスクをはらんでいますのでおすすめできません。
こちらが聞かなくても、業者側からきちんと文章で3点のポイントをクリアしていることをホームページという公の場明記してくれている、その姿勢を重視しましょう。
騙されないで!悪徳鍵業者の見分け方
騙されてしまうと本来支払う必要のない金額を悪徳業者に払うことになり、さらにまだ問題なく使用できる鍵を交換させられてしまうこともあります。そういった事態を避けるためには、業者の見極め方を知っておくことが重要です。 まず重要な点が、最終見積もりを聞いてから本格的に依頼するかどうか決められる業者を選ぶようにしましょう。
はじめに、最終見積もり次第では依頼しない可能性を伝えておくことが重要で、そのほかにはインターネットサイトを比較しておくことも大切です。安心できるサイトは逃げ道のある料金記載をしていませんし、依頼者にとって有益な情報が多数掲載されているものです。 他には業者名でのインターネット検索や公式サイト上に掲載されている実績の確認、また自社ブログをその業者が有している際にはチェックしてください。ブログは担当者の性格がよく出る部分なので、信頼に値するかどうかの見極めの際に重宝されます。あらゆる点に注意することで高額請求から身を守ることができるので、急ぎの場合であってもしっかりと行いましょう。トラブルが発生してから探すのではなく、それ以前の段階で鍵の専門業者探しを行えば、冷静な判断や見極めが可能でしょう。
鍵トラブルが発生した時に闇雲に業者選定をして依頼してしまうと、悪徳業者の餌食になりかねません。高額請求される可能性があるので注意しなくてはならず、金額についてや作業についてなどの詳細、実績や口コミなども確認しておくことがおすすめです。悪徳行為を行う業者ばかりでなく大半は信頼できるところですので、そういったところを選ぶようにしましょう。
玄関の鍵交換を業者に依頼するときの注意点
玄関の鍵交換を業者に依頼するときは、「見積もりを取る」「実績をチェックする」などを行うことが必要です。
玄関の鍵交換を業者に依頼するとき、気を付けたい注意点を紹介します。
必ず見積もりを取る
鍵の交換を依頼する際は、まず見積もりを取りましょう。
おおよその料金は、業者のホームページなどでも確認できます。ただしこれらはあくまでも概算であり、全ての鍵について適用されるわけではありません。
家庭の鍵が特殊だったり交換の難易度が高かったりする場合は、必然的に鍵の交換費用も高くなります。
見積もりを取らないままホームページの料金を鵜呑みにすると、高額な請求に驚くことになるかもしれません。
見積もりは3社以上から
見積もりを取る場合は、最低でも3社以上がおすすめです。
1社のみにすると、提示された見積もり料金が適正かどうか判断できません。高額請求に気付かず、お金をムダにする可能性があります。
2社の場合は比較ができますが、「AかBか」の2択となってしまいます。どちらも気に入らない場合、選択肢がありません。もう1社増やして3社とした方が選択の幅が広がり、信頼できる業者を選びやすくなります。
また3社から見積もりを取れば、鍵交換の相場を把握しやすくなるのもメリットです。玄関の鍵交換で、高額請求に遭うリスクを低く抑えられるでしょう。
業者の実績をチェックする
鍵の交換の仕事は、特別な資格がなくても行えます。資格がなくてもできる仕事であるため、仕事の品質には大きな差があります。玄関の鍵交換を依頼する際は、業者の過去の施工例などを確認しましょう。
業者の実績をチェックする方法は、「業者のホームページ・SNSを見る」「口コミを探す」などです。
近年は各社ともWeb展開を重視しているため、ホームページやSNSで情報を提供している業者は少なくありません。施工例について確認できることが多いため、気になる業者はネットで検索してみましょう。
また口コミサイトなどを見れば、依頼したい業者の評判が見つかることもあります。ただし口コミは、あくまでも個人の感想です。100%信用するのではなく、参考程度に留めておいてください。
業者の資格の有無を確認する
鍵の交換を依頼する際、業者の知識・スキルを測る目安となるのが「鍵師」の資格です。鍵師の資格があることで、その業者には一定レベル以上、鍵についての知識・スキルがあると見なせます。
鍵の交換を依頼しても、素人のような仕上がりになるリスクは少ないといえるでしょう。
鍵師の資格は、「ビジネス教育連盟 日本鍵師協会.」が主宰する「鍵師技能検定試験」に合格することで付与されます。
鍵師のレベルは、「2級」「1級」「マスター」の3種類です。難易度が高いのはマスターですが、、2級を持っているだけでも、錠前の専門的基礎知識や一般普及錠の取り付けについては一定レベル以上のスキルがあると考えられます。
玄関の鍵交換におすすめのメーカー
玄関の鍵を交換する場合「せっかくなら人気メーカーにしたい」「信頼性の高いメーカーにしたい」などと考える人が少なくありません。
DIYにせよ業者に依頼するにせよ、鍵の知識を付けておくことは非常に有益です。ここからは、玄関の鍵交換の選択肢に入れておきたい、おすすめの鍵メーカーを紹介します。
美和ロック株式会社(MIWA)
1945年創業の、日本を代表する鍵メーカーです。国内の建築用錠前の生産・販売では6割以上のシェアを誇り、海外でも50カ国以上の国々に販路を築いています。
美和ロック株式会社の錠前・鍵の魅力は、信頼性・防犯性が高いことです。長い歴史と伝統を持つ鍵メーカーだからこその知識・スキルが豊富に蓄えられており、一般家庭はもちろん公共施設のドアにも多くの鍵が使われています。
代表的なシリンダーとして、理論鍵違い数が約1億5千万とおりある「U9シリンダー」、リバーシブル対応の「PRシリンダー」などがあります。
株式会社ユーシン・ショウワ(SHOWA)
1998年に創業した、ドアロック・セキュリティシステム機器総合メーカーです。本社は大阪で、東京・大阪・福岡の3営業拠点で展開しています。
メインは錠前の製造・販売ですが、セキュリティシステムやカードロック・ドアロック製品なども販売しています。鍵だけではなく、セキュリティ関連全般をサポートしているといってよいでしょう。
代表的なシリンダーは、「耐ピッキング性能10分以上」の「WXシリンダー」です。鍵穴にシャッターが付いているのがポイントで、砂塵や凍結への耐性も高くなっています。
株式会社ゴール(GOAL)
1914年創業の、鍵と錠前の専門メーカーです。日本の鍵メーカーとしては初となる「米国UL防犯規格」の認定を取得しています。
時代の流れに合わせた製品開発を行っており、現在ではピンシリンダーや電気ロック・カードロックから、出入口管理システム機器・防災システム製品まで手掛けています。
一般家庭用のシリンダーには、防犯性・操作性・耐久性に優れた「AXF」「AS」などがあります。
株式会社アルファ(アルファ)
1923年創業の、住宅・産業用ロック等を手掛けるメーカーです。南京錠・電気錠・メカ錠のほか、マンション・アパート・戸建用の宅配ボックスなども製造しています。
家庭用シリンダーとしてラインナップされているのは、「FBロック」という高性能シリンダーです。鍵の先端に埋め込まれたフローティングボールが、鍵の複製やピッキングへの耐性を高めています。
対応する錠前も豊富で、MIWA製の錠前と互換性があります。
玄関の鍵交換についてのよくある質問
これまで、鍵交換についての情報をお伝えしてきましたが、ここでは、改めて鍵交換を検討する際に多くの方が抱える質問をピックアップし、回答させていただきます。
Q1. 玄関の鍵は、必ず交換しないといけないものですか?
A. 絶対に交換しなければならないという決まりはありませんが、防犯や安全面を考えると、一定のタイミングでの交換は強くおすすめされます。特に、鍵を紛失したときや、前の住人が使っていた鍵を引き継いでいる場合、ピッキングに弱い旧式の鍵を使っている場合は、被害防止のため早めの交換が安心です。
Q2. 賃貸物件に引っ越した場合、鍵は自分で交換してもいいのですか?
A. 原則として、鍵の交換はオーナーや管理会社の許可が必要です。勝手に交換すると契約違反とみなされることもあるため、まずは事前に管理会社へ相談してください。交換費用を誰が負担するかも、契約内容によって異なるため確認が必要です。
Q3. 中古住宅を購入しました。前の鍵はそのままでも大丈夫ですか?
A. できれば購入後すぐに交換するのが理想です。前の持ち主や関係者がスペアキーを保有している可能性を完全には否定できないため、防犯上のリスクがあります。新生活を安心して始めるためにも、新しい鍵に交換しておく方が無難です。
Q4. 鍵の交換は、自分でやっても問題ありませんか?
A. 自宅のドアと鍵の構造が比較的シンプルな場合にはDIYでの交換も可能です。ただし、工具の準備やサイズの確認、型番の選定を誤ると取り付けに失敗するリスクもあります。特殊な鍵や電子錠の場合は、専門業者への依頼が安全です。
Q5. 鍵の交換費用はどれくらいかかりますか?
A. DIYで交換する場合、シリンダーのみの交換であれば数千円〜1万円程度の部品代が目安です。一方、業者に依頼する場合は作業費込みで1万5千円〜3万円程度が一般的です(鍵の種類や地域、作業内容により変動します)。
Q6. 高い鍵のほうが防犯性は高いのですか?
A. 価格と防犯性能にはある程度の相関がありますが、「高い=安心」とは言い切れません。たとえばディンプルキーやCP認定を受けた鍵はピッキング耐性が高く、防犯性に優れています。価格と性能のバランスを見ながら、自宅の状況に合った鍵を選ぶことが大切です。
Q7. 鍵をなくしてしまいましたが、交換は必要ですか?
A. はい。鍵を紛失した場合は、第三者が拾って不正に使うリスクがあるため、速やかに交換することをおすすめします。「あとで見つかったから大丈夫」と判断するのは危険です。特に住所と紐づいた場所で失くした場合は、早急な対応が必要です。
Q8. 合鍵を作るときに注意することはありますか?
A. ディンプルキーなどの防犯性能が高い鍵には、登録カードがないと合鍵を作れない「管理型」のものがあります。無断複製を防ぐためにこうした仕組みが導入されていますので、紛失や盗難に備えて登録カードの保管場所も注意しておきましょう。
Q9. 鍵交換後も、定期的にメンテナンスが必要ですか?
A. はい、必要です。ホコリや汚れの蓄積、鍵の摩耗が原因で動きが悪くなることがあります。定期的にエアダスターでの清掃や、潤滑剤の使用を行うことで、長く快適に使い続けることができます。異常を感じたら早めの点検・交換を検討しましょう。
Q10. 鍵の交換はどこに依頼すればいいですか?
A. 鍵の専門業者や防犯設備士が在籍する会社への依頼が安心です。依頼前に、料金・対応地域・見積もりの明確さ・実績などを比較するとよいでしょう。悪徳業者を避けるためにも、「見積もり後に追加料金が発生しない」と明記されている業者を選ぶのがポイントです。
まとめ
玄関の鍵交換は、既存の鍵がどんなタイプかを理解したうえで、ドアの規格なども忘れずに調べ、それに適合する鍵を間違いなく選べば、DIYでおこなうことも可能です。
ただし、DIYでの鍵交換は当然のことながらすべてが自己責任となりますので、交換作業に慣れていない素人にとってはハイリスクな部分もあります。
無駄なリスクを避け、安心安全かつ確実な鍵交換をしたいのであれば、やはり鍵交換を得意とする専門業者に依頼するのがおすすめです。
見積もり無料で見積もり後の追加料金なし、もしもの事態のときには損害賠償もできるということをホームページなどで明記している良心的な業者を選ぶようにしましょう。
この記事を監修した専門家
監修 (一社)日本刑事技術協会
代表理事
森 透匡
(もり ゆきまさ)
元千葉県警の警部。約20年にわたり、詐欺、横領、贈収賄などの知能・経済犯罪を筆頭に、殺人事件、薬物事件、組織犯罪などの犯罪捜査に従事。現在は一般社団法人日本刑事技術協会の代表理事として15名以上の警察OBが所属する団体を運営し、多種多様な犯罪に関する防犯講演、商品監修、TVなどのマスコミ出演、マッチングアプリ大手運営会社の詐欺防止に関わる有識者会議委員、「高齢者を身近な危険から守る本」の監修など知見を活かした幅広い活動に尽力している。
この記事は、玄関の鍵交換に関する費用やDIYでの交換ポイント、注意点について詳細に解説しています。この記事は家庭での防犯対策の一環として非常に役立つ情報を提供しています。特に、鍵の種類ごとの防犯面の高さや、DIYでの鍵交換時のリスクについての説明は、安全意識の高い住環境づくりに貢献する内容です。しかし、専門的な作業やセキュリティの高い鍵交換に関しては、専門業者への依頼を推奨するのが妥当と考えます。
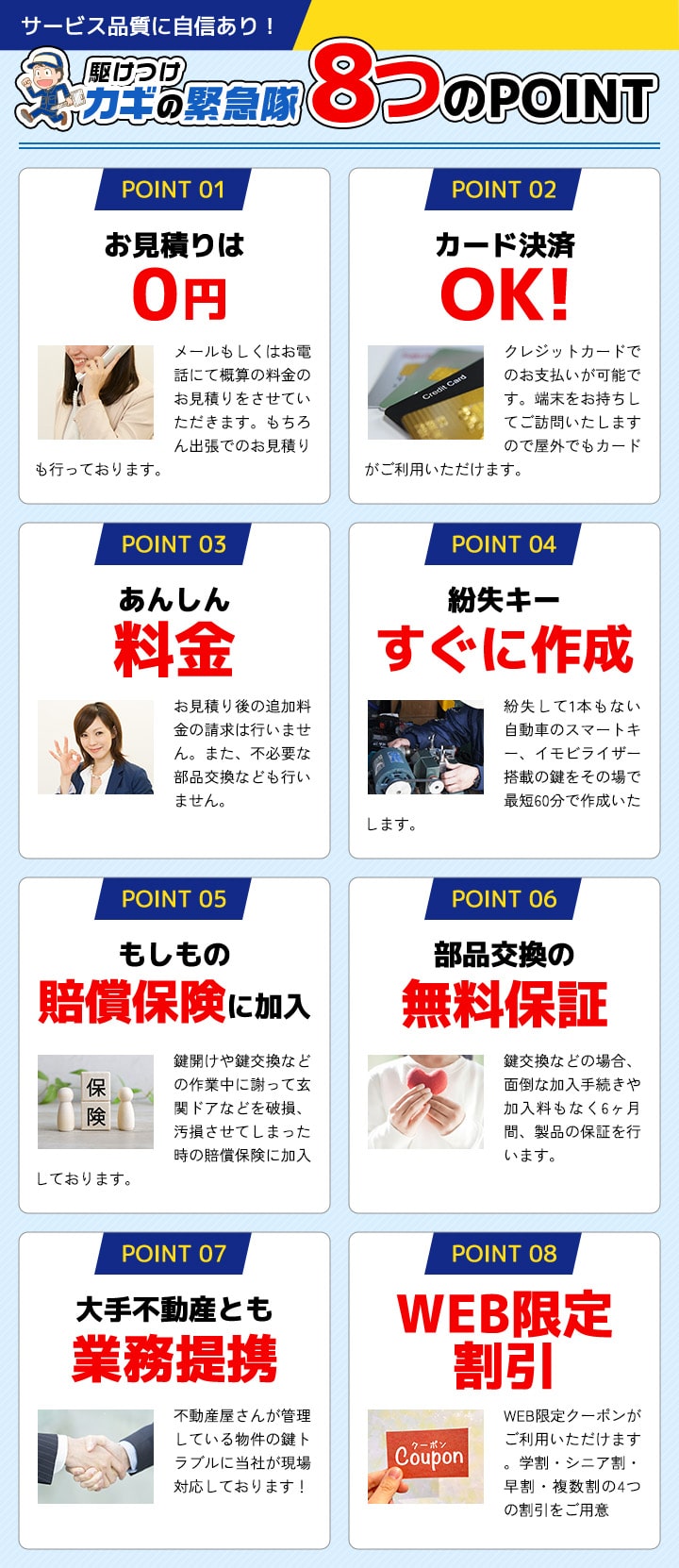
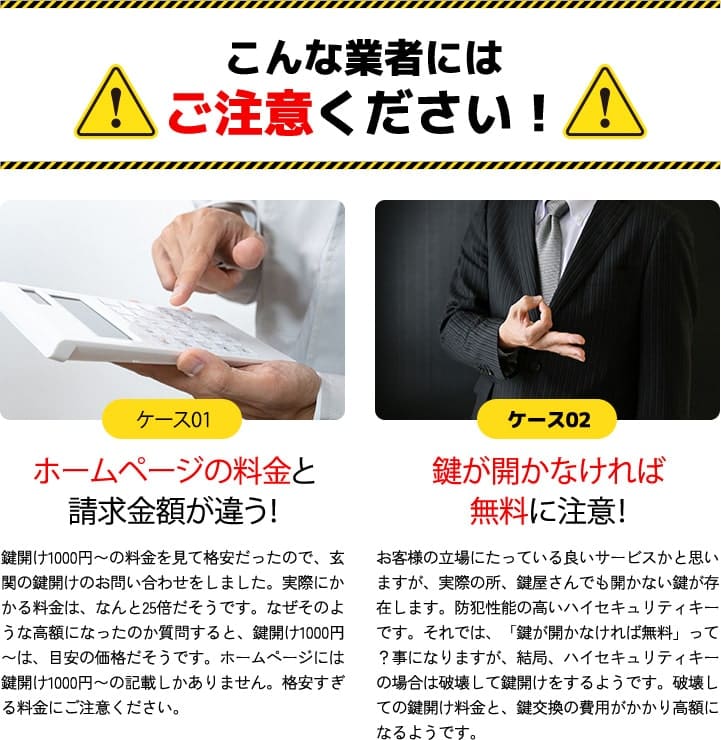
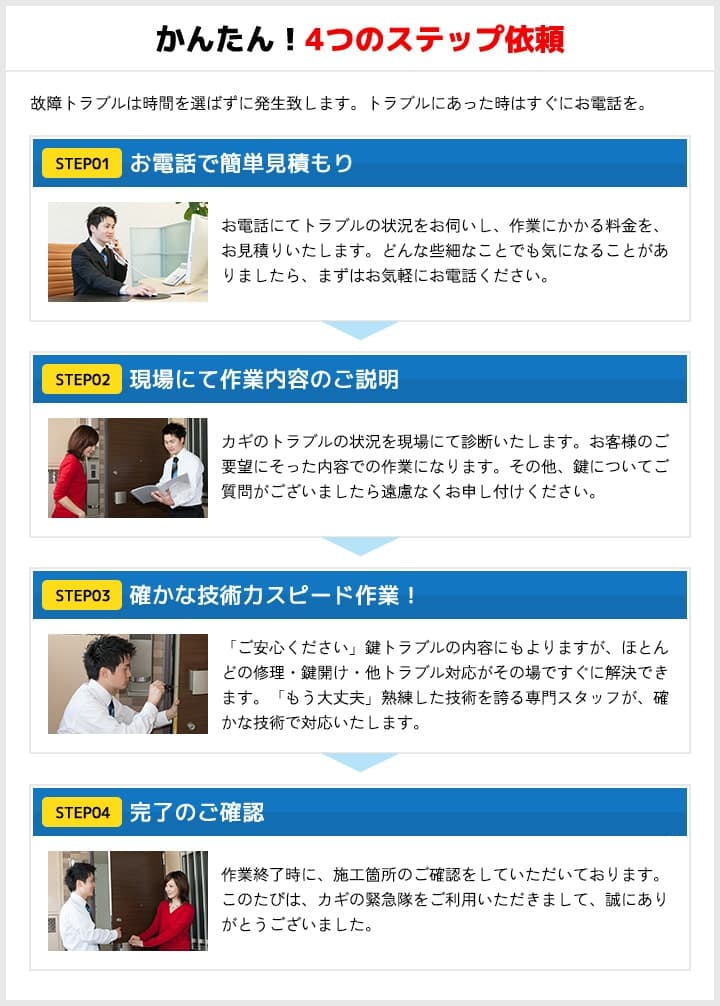
便利なお支払い方法も充実!

※1クレジットカードによるお支払いには、お客様ご本人名義のクレジットカードのみご利用いただけます。※エリアなどにより一部ご利用いただけないクレジットカードの種類がございます。
※2後払いご希望の方は、予めメールでお伝えください。一部対応していないエリアもございますのでご了承ください。






